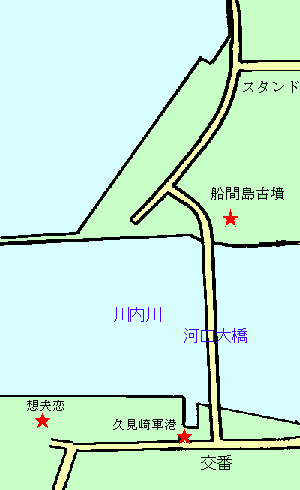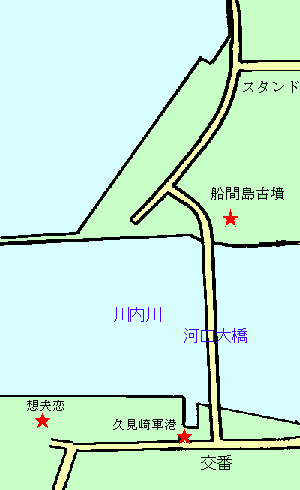 |
船間島古墳
川内川河口大橋を久見崎側から渡ると橋の終わり付近進行方向右手に小高い山が見えてきます。
そこには薩摩川内市によって立てられた看板には船間島古墳と記載されてあるにゃ。
この古墳は、川内川流域に見られる地下式古墳のもっとも西にある古墳であり
6〜7世紀に作られたものだそうです。
この古墳の主が誰なのかはなぞなのですが、身分の高い方だったらしく
石室は朱色にぬられ
古くからこの地域の人に手厚く祭られていました。
この地は、古くはニニギノミコト伝説で水先案内人の船間島十郎という方を葬った伝説もありますが
川内川河口のこの地は、古くから中国などとも交易があつたようですからきっと
渡来人のお墓かもしれませんね。
久見崎軍港
時代は江戸時代になりますが、ここ川内川の河口は薩摩藩の軍港でした。
当時としては珍しく、ドックを備えたもので、大平橋下の渡唐口との間に貨客船がでるなど栄えた港だったそうです。
現在は、その面影はなく、1枚の看板に説明があるのみです。
想夫恋
毎年旧暦のお盆になると、河口の久見崎では盆踊りとして「想夫恋」という踊りが行われています。
この踊りは、秀吉による朝鮮出兵の際亡くなった島津の兵の霊を鎮魂するために残った家族がはじめたと言われ、
男物の紋付きに黒い布で顔を包み三味線に太鼓と純粋の鎮霊歌といった感じです。
|